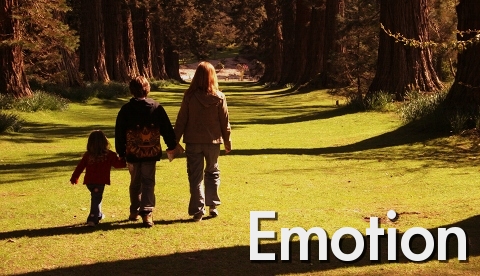ある公園の風景
by Saito 2013年04月15日家の近くには結構大きめの公園があるのですが、先日そこで昼間ぼんやりしていると「それはママに見せなさい!」という子供の声が聞こえてきました。なにかお母さんに報告でもあるのかと数人の子供が集まってしている話に耳を傾けると、どうやらおままごとをしているご様子。「ままごとってあったなぁ」と懐かしく思っているとママ役の子がまた「ちょっとママに見せなさい!」と、子供役の男の子が手に持っているなにかを見せろ見せろとしきりに言ってました。何を持っているのかまでは分からなかったのですが、その前後の会話の内容から虫か小鳥くらいの大きさのものが死んでいるのを見つけた様でした。以下子供達の会話です。
「誰がやったのかなぁ?」
「自然とこうなったんじゃない?」
「ねえ、この子に名前つけてお墓作ってあげようよ」
「はくちゃん!」
「嫌だ〜」
「ねえ、どうしようか?」
「交番に届けよう」
「どうかな?」
「でも落とし物じゃないよ」
「俺花探してくる!」
「じゃあ花を探す係とお墓作る係を作ろうか!」
行ったり来たりで振り回されてる亡きがらには可哀想と思いつつ、久々に聞いた子供達だけの会話はなんだかとても微笑ましかったですね。結局どうなったか事の顛末は見届けず家に帰りましたが、木々の緑に囲まれながらその子供達の会話はどうにも印象的でした。昼下がりの公園にはそんな魅力がありますね。
真田十勇士
by Saito 2013年04月9日笹沢左保さんという作家の「真田十勇士」という作品をご存知でしょうか?これはもう大分前に一度読んだいわゆる歴史小説なのですが、なぜか最近また読み返してしまいました。真田十勇士自体は昔からあるもので、現在伝わっているこの物語はまだテレビやラジオも無かった時代に「講談師」と言われた方達が町々に訪れてしていたお話が元になっているそうです。戦国時代末期の史実をもとにした架空のお話なのですが、その時代の大勢ではない豊臣側へ敢えて加勢する真田幸村という武将のもとに一騎当千の十人集が大活躍するという、この昔の人の想像力の逞しさはいつ触れても脅威を憶えますね。何百年後かには現在生きている人達にも、もしかしたらそういった架空のお話が出来ているのかも知れませんね。
滅びの美学
今回読み返して一番思ったのがこの日本特有とも言われる「滅びの美学」についてです。もっと上手いやり方もあるのに、敢えて滅びる方へ向かっていく。自分の信念を貫くため、むしろ滅びていく事に美しさを見いだすとでも言いましょうか。それ自体には前と同じように血が騒ぐところがあったのですが、なんだかんだ周りの上手く行ってない感じにイライラを憶え「こんな形で滅びていくのは嫌だな」と今回読み返してみて単純に思ってしまいました。なぜそう思ったのか不思議な感じが自分でもしましたね。物語は何一つ変っていないのに自分に流れた時間がそう思わせたのか…。たまには以前読んだ本を読み返してみても、色々な事に気付かされて良いものだと思いました。
Discovery Nippon(動画フェス)
by Saito 2013年04月1日ついにスタート致しました、動画フェス2013。
動画フェスとは誰でもご参加頂ける動画コンテストで、テーマに沿った動画を募集しています。2013年の9月末までにエントリーして頂いた作品の中から、各審査員が選考し11月1日に大賞を発表させて頂きます。
そして記念すべき第一回、2013年のテーマは、『Discovery Nippon / 日本を見つけよう』です。
普段何気なく見過ごしているもの、ただ当たり前すぎて気に留める事は少なくても、私達はこの「日本」というものが持つ風土また文化や芸術、その味わい深さを肌で知っている。そんなところから改めて「見つけよう」という言葉を使わせて頂きました。皆様の周りにあるそういったものを、動画という媒体を使って沢山の方に教えて頂ければと思います。
そして是非ご一緒にこの「日本」が持つ味わい深さを再発見していきましょう!

動画フェス http://www.moviefes.com/
感動の余韻
by Saito 2013年03月25日最近何に感動したでしょうか?例えば映画、本、または景色。「感動」というものは、この目には見えない、ましてはっきりとした形にして残しておく事の出来ないものです。だからこそ尊いものなのかなとも思います。
何かによって感情を動かされるということは、日常の中に結構転がっているように思います。ふとした瞬間に訪れて日々の生活を彩ってくれるのですが、たまに人生を変えてしまうくらいの大きなものも、同じ様なさりげなさで訪れる事もありますね。大好きな人と出会ったり、好きなものを職業にしたりというのもその一例でしょうか。そこまで大袈裟なものではなくても、その瞬間に訪れる感動というのは、時が経つにつれ形を変えながら、ずっとどこかに残っているような気がしますね。もともと形が無いものだからこそ変わっていけるという気もします。そしてこの余韻のようなものが気が付かないうちに呼び水となって、また新たな感動との出会いを与えてくれているように思います。